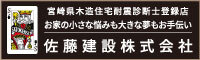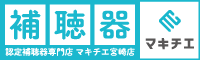| 番号 | 名称 | 所在地 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎城跡(池内城・龍峰城) | 池内町 | 南北朝期に築かれ、延岡藩の城として一国一城令で廃城となるまで利用された山城で、曲輪や塀が残る。伊東義祐や上井覚兼等の武将がいたことで知られ、関ケ原合戦の際、稲津重政が権藤種盛の守るこの城を攻め、落城させている。上井覚兼の日記から当時の様子を窺い知ることができる。 |
| 2 | 倉岡城跡(池尻城) | 大字糸原 | 大淀川に張り出した標高約40mの丘稜にあり、本丸・二の丸・三の丸跡が残る。応永年間に島津久豊が築き、伊東氏の時代には48城の一つであったが、その後は島津氏が所有。一国一城令で廃城。 |
| 3 | 石塚城跡 | 大字浮田 | 水田中の丘を利用した城で、本丸と二の丸に分かれる。伊東祐武の居城として応永年間(1394~1428)に築城された。伊東48城の一つ。 |
| 4 | 曽井城跡 | 大字恒久 | 南を古城川に臨む平山城で、曽井祐善が築いたとされる。伊東氏と島津氏の争奪戦が繰り返され、伊東祐兵が飫肥に移るまで利用された。伊東48城の一つであり、一国一城令で廃城となる。 |
| 5 | 車坂城跡 | 大字熊野 | 南に加江田川を控える丘陵にあったが、運動公園・学園都市建設の際、消滅している。天授年間(1375~1380)に熊野氏によって築かれ、その後、伊東氏と島津氏の間で争奪戦が繰り返された。 |
| 6 | 紫波洲崎城跡 | 大字折生迫 | 青島の南、海を隔てた丘陵上に筑波川や日向灘等自然地形を利用して築かれた山城で、伊東48城の一つ。天正時代には上井覚兼の父、薫兼が居城した。一国一城令により廃城。 |
| 7 | 伊満福寺 | 古城町 | 日向七堂伽藍の一つで、全国四十九大伽藍の一つにも加えられる古刹である。平安時代に創設されたと伝えられ、奥の院も含め多数の石仏、石塔が群立している。 |