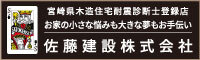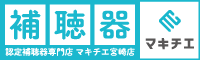宮崎市教育・保育施設等重大事故検証委員会報告書について
令和5年3月に市内の認可外保育施設で発生した乳児死亡事案を対象とした「宮崎市教育・保育施設等重大事故検証委員会」を設置し、これまで委員会を4回開催してきました。
本検証委員会においては、子どもの権利条約にも明示されているとおり、すべての子どもの「生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)」が保障されるべきであるとの前提に立って、本事案を非常に重く受け止め、再発防止のため、事実関係の把握や発生原因の分析等を行ってきました。
この度、検証委員会において、事故防止のための対策に関する提言を盛り込んだ報告書がまとめられ、市長へ提出されましたので、お知らせいたします。
検証委員会の設置
令和5年3月に市内の認可外保育施設で発生した死亡事故について、国の通知※に基づき、外部委員5名(学識経験者、医師、弁護士、教育・保育関係者)で構成する検証委員会を設置しました。
※「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について(平成28年3月31日付け府子第191号等内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども。子育て支援担当)等通知)
検証委員会の開催
| 会議回 | 開催日 |
| 第1回 | 令和5年7月19日 |
| 第2回 | 令和5年9月27日 |
| 第3回 | 令和5年12月5日 |
| 第4回 | 令和6年2月8日 |
令和6年度 事故防止に向けた行政の取組みの見直しと強化について
検証委員会から受けた行政に対する5つの提言について、対応状況を報告します。
提言1 保育に従事する職員(配置数や資格)について、行政の監査を強化する
[対応]監査での重点項目の設定と施設への事前周知を行っていく。
[対応]外部を交えての勉強会を開き、現場や有識者の助言を取り入れながら改善を行っていく。
[令和6年度の対応結果]
令和6年度の監査において、重点項目を定め、子どもの安全や事故防止に関する内容及び職員の配置状況等を重点的に確認を行いました。
また、令和7年度の監査実施に向け、令和7年3月に有識者及び教育・保育施設の関係団体との1回目の勉強会を開催。より実効性のある監査を行うため、勉強会を通じて有識者や関係団体からの助言をいただきながら引き続き監査方法のブラッシュアップを行っていきます。
提言2 保育の質をアップするために、幼児教育・保育に関する専門職を配置する
[対応]専門職を配置する。
[令和6年度の対応結果]
保育所や幼稚園等から小学校へのスムーズな接続の推進を図るために配置している「保幼小連携アドバイザー」に新たな役割を付加し、令和7年度からは「教育・保育業務支援アドバイザー」として業務を行います。
●新たに付加した役割
・園を訪問し、好事例の集約及び周知
(※R6集約した好事例集R6【好事例集】教育・保育施設の取組について (PDF 768KB))
・質の向上に資する研修会の企画、開催
・教育、保育に関する助言等
提言3 保育従事者研修機会の確保、研修に関する情報の集約や周知の徹底及び受講状況の確認を指導監査において行っていく
[対応]保育会・幼稚園協会への補助事業の中で、認可外施設も対象とした研修を開催する。
[対応]研修に関する情報の集約や周知の徹底。
[対応]受講状況に関する監査時の確認。
[令和6年度の対応結果]
教育・保育関係団体と連携し、団体が研修会等を開催する際は“認可外保育施設”にも案内を行うなどして、参加促進を図りました。
外部団体が実施する研修会についても、市へ案内があったものについては遺漏なく周知を徹底し、事故防止のための園内研修の実施状況(外部研修会の受講状況含む。)については、令和6年度の重点項目に位置づけて確認を行いました。
提言4 子どもの死が発生した際の対策を強化する。CDR(child death review)事業を開始する、家族へのグリーフケア体制づくりを行うなど
[対応]CDR事業について、県への要望を行う。
[対応]家族へのグリーフケアの体制づくりの検討
[令和6年度の対応結果]
令和6年7月に、県に対して「予防のためのこどもの死亡検証体制整備に係る取組」について、要望活動を行いました。家族へのグリーフケアの体制づくりについては、関係課に情報収集を行っている段階であり、引き続き検討を行っていきます。
提言5 子どもの安全確保に有用な機器や設備の保育施設への導入を促進するための施策を検討する
[対応]R7新規事業として構築するか、検討を行う。
[令和6年度の対応結果]
令和7年度事業として「午睡システム等公立保育所ICT化推進事業」を新たに構築。まず、公立保育所において午睡管理機器を導入し、機器導入の有効性や補完性などの効果を検証し、機器利用にかかる留意事項をまとめます。