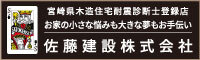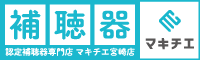令和7年9月14日(日)、宮崎公立大学にて『耳の聴こえと認知症講演会』を開催し、138名の方にご参加いただきました。
講演会の内容をご紹介します。
【講演1】耳の聴こえを保つということ

【講師】宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頚部外科学分野 髙橋邦行教授
【内容】
・「聴こえる」とは、積極的に聞くことで、音声によるコミュニケーションは、音から言語概念を形成することで思考にも影響を与え、学習や発達、認知機能に密接に関係している。
・難聴は聴こえる音の大きさで程度が計られ、普通の会話が聴こえる程度である40dbの難聴であっても、普通の会話がごく小さな声にしか聞こえず、はっきり聞き取れないことがある。正常の人が耳栓をしている感じに近い。
・加齢によって生じる難聴は、高音が聞き取りにくくなり、会話に必要な音の高さと大きさがあることから、聞き間違いが生じることがある。
・認知症の要因の40%は予防可能と言われており、なかでも難聴が最大の修正可能な危険因子となっている。
・軽度難聴でも認知症の発症リスクが1.89倍、中等度難聴では3倍に増加することが分かっており、軽度難聴のうちから対策をすることが重要であるが、加齢による難聴は自覚されにくい。
・難聴の種類には「伝音難聴(約10%)」と「感音難聴(約90%)」とがあり、前者は手術で治療が可能であるが、後者は加齢や大きな音の影響により音を伝える細胞が障がいを受けることから起こる難聴であることから回復はしない。
・難聴への治療には「補聴器」と「人工内耳」があるが、人工内耳は、補聴器で効果のない人に対して使用するものである。どちらにしても、聴こえの低下を感じたら耳鼻科を受診する。補聴器を使用する場合、定期的な診察と管理が必要となる。
・補聴器が日本で普及しないのは、欧米の言語よりも低い音が多く、会話が成り立つことから気づきにくいことと、補聴器は格好悪いというイメージがあるため。
・補聴器購入に対して助成を行う自治体があるが少ない。宮崎県では三股町、新富町、諸塚村、日之影町、宮崎市である。
・聴こえを保ち、家族との団らんや友人との交流、認知症予防につなげてほしい。
【講演2】睡眠と脳の健康について

【講師】宮崎大学医学部精神医学分野 平野羊嗣教授
【内容】
・睡眠は記憶の定着、成長、細胞の修復、ストレス解消、免疫力回復、疲労回復など、体のメンテナンスにとって、重要な役割を担っている。
・適切な睡眠時間として7時間が推奨されており、短すぎても、長すぎても睡眠のリズム(約90分周期)が崩れ、認知機能低下や免疫力低下につながる。不眠は、うつ病、不安障害、依存症などの精神疾患や胃腸障害、慢性疼痛、糖尿病などの身体疾患のリスクを上昇させる。
・脳は寝ている間に「グリンパティックシステム」という仕組みで脳内の老廃物を掃除している。睡眠が障害されると脳内に老廃物が蓄積し、認知機能低下につながる可能性がある。
・睡眠衛生指導によると、ベッドは寝るためだけの場所にする、アルコールやカフェインは控える、眠くなるまで起きておく、起きる時間を一定にする、起きたらすぐに日光を浴びる、生活のリズムを整えることが重要である。
・アルコールは睡眠が浅くなり、カフェインは覚醒作用があるため、午後は控える方がよい。
・「ベンゾジアゼピン系」の睡眠薬は、依存性や副作用のリスクがあり、睡眠薬を原因として発生した事件の多くは、ベンゾジアゼピン系睡眠薬によるものであると指摘されている。医師に睡眠薬を処方してもらう場合は、「メラトニン受容体作動薬」と「オレキシン受容体拮抗薬」を処方してもらうように。
・「認知症」は体験全体を忘れるもので、ヒントがあっても思い出せないが、「物忘れ」は体験の一部を忘れるだけで、ヒントがあれば思い出せる。
・難聴は認知症リスク因子の一つとなっていて、認知機能低下を加速する可能性がある。
・認知症予防には、糖尿病やコレステロール管理、血圧管理、禁煙、体重管理、うつ病予防、難聴や視力障碍への対応、社会活動、運動が重要である。特に、軽度認知障害(MCI)の段階での予防が肝要である。
【パネルディスカッション】補聴器を正しく使って生活を豊かに

【パネラー】宮崎県耳鼻咽喉科医会 会長 坪井 康浩 氏
宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野 教授 髙橋 邦行 氏
宮崎大学医学部附属病院 難聴支援センター 永友 陽菜 氏
【内容】
司会:事例の中では夫婦の会話に支障を感じたことが補聴器をつけるきっかけということでした。このきっかけは、早いのか遅いのか、外来を多く診ていらっしゃる坪井先生からお願いします。
坪井先生:補聴器をつけるきっかけでは、家族が補聴器を付けてほしいからとか家族からのプレゼントというものが多いです。ただ、本人自体には困り感がないので、急に補聴器をつけてうるさく感じて、無理に付けさせられた印象と合わさって、補聴器をつけなくなってしまいます。大事なのは本人に聴こえない実感があることで、補聴器をつけないといけないと納得するかどうかだと思います。普段の会話が続かないとか成り立たないのが困るという気づきを本人に与えられるかどうかが大事だと思います。
司会:本人だけでなく、家族にとっても有益な情報でした。坪井先生、ありがとうございます。事例では、何度も補聴器を調整するのが長く使う上で大事とありました。また、会場から補聴器の値段についてもご質問がありました。こちらについては、永友先生に教えていただけますでしょうか。
永友先生:聴こえにくさの程度は人それぞれです。低い音から高い音までがどのように聴こえにくいのかということに合わせて、どれくらい音を大きくしていくのか調整していくことが必要となります。今まで聴こえていなかった音が入ってくるため、最初から100%の音を入れてしまうと、うるさくて使えない方が多いです。快適に使える音の大きさから慣れていってもらい、そこから音量を上げていくことを繰り返して目標となる音量まで調整していくため、調整は頻回に必要となります。「どれくらいで慣れるのか?」という質問については、聴こえの程度によって人それぞれで、聴こえがすごく悪い方は、補聴器がないと聴こえないので慣れやすい印象です。しかし、補聴器をつけなくてもある程度お話しができる方など、軽度から中等度難聴の方は時間がかかる印象です。3ヶ月から半年はみてもらった方が良いと思います。まずは、補聴器を購入するのではなく、1ヶ月くらいお試しをした上で補聴器があった方が生活に役立つか考えてもらってからが良いと思います。値段については、10万前後の補聴器でも音を大きくする機能は十分だと思います。
司会:人工内耳についてもう一度お話を聴かせてください。また、難聴の予防についても教えてください。
髙橋先生:補聴器でも言葉の聴こえが不十分な方(6割未満)の方は検討しても良いと思います。ただ、人工内耳を入れても7割くらいの聴こえにしかなりません。聴こえなくなってから何年経っているかということも重要です。去年まで補聴器で聴こえていましたという方は手術すると聴こえるようになるケースが多いです。10年以上経っている場合は厳しいです。予防については、大きな音を入れないことにつきます。内耳の有毛細胞が揺れることで聴力が落ちてしまいます。大きな騒音がする飛行機の中では、ノイズキャンセルイヤホンをしています。満員電車や飛行機で音楽を聴くとなると、騒音の音量よりも大きな音で聴くことになってしまいます。
司会:若い方もなるべく大きな音を控えるということが大切ですね。ここで、会場の方から質問を受けつけたいと思います。
質問者1:難聴の予防はどうしたらよいのでしょうか。夫が片耳が聴こえず、生活音の中でキーンとすることがあるようです。これらは補聴器で治るのでしょうか。
髙橋先生:大きな音がしている中で必要なものを聴こうとするとさらに大きな音が必要になってしまいます。TV本体の音量をあげるよりも、首にかけるヘッドフォンをしてできるだけ小さい音で聴くようにする方が良いです。聴覚過敏については、内耳性の難聴では『聴こえない』、『耳鳴り』、『つまった感じ』、『響く』の4つの症状がセットです。それぞれの程度には個人差があります。補聴器で改善するかについては、永友先生どうですか?
永友先生:響くことを補聴器で改善するのは難しいです。響きが強い方は、補聴器に慣れるまでに時間がかかることが多いです。
髙橋先生:耳鳴りについては、誰でも無響室などに入ると聴こえることが多いですが、環境音の中でかき消されて分からなくなります。補聴器をつけると他の音が入ることで耳鳴りは楽になることは多いです。聴覚過敏に対しては、補聴器で急に音が入ったときに抑制してくれる機能はあります。耳の過敏を治すということはまだ研究課題であります。
質問者2:イヤホンをつけると難聴になるリスクが上がるということですが、骨伝導イヤホンも同じでしょうか。
髙橋先生:基本的には大きな差はないと思います
司会:最後にパネリストの先生からメッセージをお願いします。
髙橋先生:少しでも困ることがあったら、早目に耳鼻咽喉科の受診をしてほしいです。気付いていないレベルでも難聴の可能性があります。もう一つは、若い方と同じように意欲をもっていただきたいです。会話に入っていくぞという気持ちをもってほしいと思います。
坪井先生:宮崎市は今年の6月から補聴器購入助成を開始しています。耳鼻科で認定を受けられた方は積極的に利用してほしいと思います。
永友先生:聴こえにくいと感じた場合や、周りから指摘された場合は早目に耳鼻科に行ってほしいです。自分の聴力を知っていただき、補聴器が必要かどうかをきちんと理解することが大切だと思います。
司会:早目の気づきと早目の受診がポイントですね。パネラーの先生方ありがとうございました。