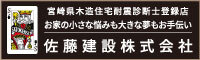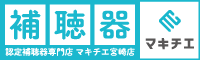目次
(1)お知らせ
小児慢性特定疾病の対象疾患追加について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾患は、令和7年4月1日から801疾病に拡大しました。
小児慢性特定疾病における成長ホルモン治療の認定不要について
小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療を行うための基準が廃止され、令和6年4月1日からは「成長ホルモン治療用医療意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となりました。
(2)小児慢性特定疾病の制度概要について
児童の慢性疾病のうち国が指定する特定の疾病(小児慢性特定疾病)について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険適用分を除いた自己負担分)の一部を公費により負担し、小児慢性児童のご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。
詳しくはみやざきっ子ガイドブックをご覧ください。
※みやざきっ子ガイドブックについて
小児慢性特定疾病をもつお子さまが、療養生活を送る上で安心して日常生活を過ごしていただけるよう、各種制度に関する内容・相談窓口などを掲載しています。
紙面の都合上、本文は簡単な説明となっております。また法律の改正などで、記載されている内容に変更が生じる場合があります。(令和5年4月作成時の内容)
詳しくはそれぞれの担当課までお問い合わせください。
対象者
保護者または本人が宮崎市内に住所を有する18歳未満の児童
※ただし、支給認定を受けている方で継続治療が必要な方は、20歳の誕生日の前日まで医療費の助成を受けることができます。
対象疾病
対象となる医療と自己負担額
小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている疾病に対して、指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で行われた医療のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して、医療費の補助が受けられます。
※自己負担上限額表 (PDF 823KB)
自己負担上限月額管理票について
自己負担上限月額管理票は、1ヶ月の自己負担(患者負担割合:2割)が上限額を超えることがないよう、医療機関や薬局の窓口で確認するために使用するものです。
自己負担上限額管理票等の記載方法等について(厚生労働省通知)
(3)申請について
申請に必要な書類
2医療意見書 (※指定医が記入。)
3調査研究にかかる同意書 保護者向け研究同意書リーフレット(厚生労働省作成)
6対象児の加入医療保険の資格情報が確認できるもの(本人が国保組合の場合は、世帯全員分)
「マイナポータル資格情報の画面コピー」または、「資格確認書の写し」または、「従来の健康保険証(R7.12.1まで)」
7マイナンバーカード(対象児及び世帯内で対象児と同じ医療保険に加入する方の分)
8(更新のみ)自己負担上限月額管理票のコピー方法
[申請先]〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1-6-2 宮崎市親子保健課
支給開始日の遡りについて
令和5年10月1日から支給開始日がこれまでの「申請日」から医療意見書に記載された「診断年月日」等へ遡ることができるようになりました。
診断年月日とは、指定医が疾病の状態や程度を満たしていると診断した日のことです。
支給開始日は診断年月日を最大として、申請日から原則1か月、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで遡ることができます。
こんな時は届出が必要です
加入医療保険の資格情報が変わった場合
3対象児の加入医療保険の資格情報(本人が国保組合の場合は、世帯全員分)
「マイナポータル資格情報の画面コピー」または、「資格確認書の写し」または、「従来の健康保険証(R7.12.1まで)」
上記以外で受給者証の記載内容(住所等)が変わった場合
高額治療継続者、重症患者、人工呼吸器等装着者の認定を受けるとき
2重症患者認定申告書+医療意見書または障がい者手帳(障がい年金証明書)の写し
4自己負担上限額管理表の写しまたは領収書の写し 自己負担上限月額管理票コピーの方法
※新規申請時以外に申請される場合は、申請した翌月から適用となります。
※高額治療継続者とは…
自己負担上限額が5,000円以上の方で、医療費総額(10割)が5万円を超える月が、認定日以降、年6回以上ある場合、上限月額が軽減されます(申請した翌月から適用)。詳しくは親子保健課までお問い合わせください。
(4)指定医
小児慢性特定疾病医療費助成制度を受けるためには、あらかじめ都道府県知事(政令・中核市は当該市長)から指定を受けた医師(指定医)が作成した診断書(医療意見書)を添えて申請する必要があります。
指定医の指定を受けるためには、主として診断書(医療意見書)を作成する医療機関が所在する都道府県(政令市・中核市は当該市)への申請が必要です。
[申請先]〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1-6-2 宮崎市親子保健課
指定医の要件
・小児慢性特定疾病指定医指定要領(R7.6.17現在) (PDF 96.1KB)
指定医研修について
平成29年度まで研修会を開催しておりましたが、平成30年度より指定医研修サイト(インターネット講座)【外部リンク】による研修を行います。研修実施概要に従って受講後「修了証」が発行されますので、指定医申請時に添付をお願いいたします。
医療意見書
令和5年10月1日より、制度の変更に伴い医療意見書の様式が変更となり、新たに「診断年月日」等を記入する項目が追加されました。
「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページ(外部リンク)から様式をダウンロードできます。
また、医療意見書作成時には、療育指導連絡票も記載し、一緒に提出していただきますようお願いいたします。
令和5年10月1日より医療意見書のオンライン登録(難病・小慢データベース)が実施されています。
厚生労働省より情報が公開されておりますのでご確認ください。厚生労働省ホームページ【外部リンク】
支給開始日の遡りについて
令和5年10月1日から支給開始日がこれまでの「申請日」から医療意見書に記載された「診断年月日」等へ遡ることができるようになりました。
診断年月日とは、指定医が疾病の状態や程度を満たしていると診断した日のことです。
支給開始日は診断年月日を最大として、申請日から原則1か月、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで遡ることができます。
新規申請
・新規申請
申請内容の変更・辞退
更新申請
・更新申請
指定医一覧
(5)指定医療機関
小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県知事(政令・中核市は当該市長)から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関が行う医療に限り、医療費助成の対象となります。
宮崎市に所在する医療機関は宮崎市長の指定を受ける必要がありますので、下記の様式にて申請手続きを行ってください。
[申請先]〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1-6-2 宮崎市親子保健課
新規申請
医療機関コードの変更
申請内容の変更(医療機関コード以外の変更)
更新申請
辞退
指定医療機関一覧
・小慢指定医療機関(R7.10.16現在) (PDF 114KB)
・小慢指定医療機関(歯科)(R7.4.22現在) (PDF 37.4KB)