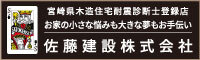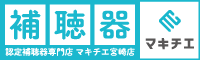梅毒急増中!
2021年以降、全国的に梅毒感染者の届出数が増加しています。
2023年の国内報告数は15,078人となり、届出制となった1999年から過去最高の報告数となりました。
宮崎市内でも、2019年以降届出数が右肩上がりに増加しており、2023年には過去最高の111件(男性:64件、女性:47件)の届出がありました。
宮崎県は、2023年第4四半期(第40~52週)の人口100万人あたりの報告数が47都道府県中ワースト5位となっています。
男性では20~50代、女性では20~30代の報告数が多い傾向です。
【2014~2023年の梅毒発生状況(全国・宮崎県・宮崎市)】

梅毒について正しく知りましょう
梅毒とは
梅毒は、「梅毒トレポネーマ」という細菌が主に性的な接触によって感染し、しこりや発疹などのさまざまな症状が出る病気です。ごくまれに、皮膚や粘膜の傷から感染することがあります。
検査や治療の開始が遅れたり、治療せずに放置したりすると、長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を引き起こすことがあります。
梅毒は、感染力の強い感染症です。
妊娠している人が梅毒にかかると、流産、死産となったり、子が梅毒にかかった状態で生まれる先天梅毒となることがあります。
梅毒の感染経路
性行為における接触感染が最も多い感染経路ですが、血液感染や母子感染もあります。
性行為には、オーラルセックスやキスも含まれます。
梅毒の症状
梅毒の症状は、段階的に進行します。
下記は、治療を行わなかった場合の典型的な経過です。
| 1期(3週~) | 性器・肛門・口に3mm~3cm大の痛みの無いできものが出現。2,3週間で消失。 |
|---|---|
| 2期(3か月~) | 手のひら・足の裏・体に赤い発疹が出現(バラ疹)。数週で消失。症状が出たり無くなったりを繰り返すことがある。 |
| 3期(3年~) | 全身で炎症が進行。 |
| 4期(10年~) | 脳・心臓に病変ができることがある。進行すると、眼・脳・心臓などに障がいが出て失明したり、認知症や麻痺の症状を来すこともある。 |
※これらの症状は時間がたつと自然と消え、次の段階の症状が出現するため、気がつきにくい、また感染していても症状が出ない人もいるため注意が必要です。
梅毒の検査方法
採血をして、梅毒の抗体が体内にあるかどうかを調べます。
梅毒の抗体は、感染から間もない時期では量が少なく、検査しても陽性にならないことがあります。そのため、新しく感染を心配する性的接触があった場合、1カ月以上たってから検査を受けるとようにしましょう。
宮崎市保健所では毎週月曜日に検査を行っております。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
www.city.miyazaki.miyazaki.jp/health/health/infection/354.html
梅毒の治療法
梅毒は早期の適切な抗菌薬治療で完治が可能です。
ただ、十分に治療されないと病気が進行することもあるため、症状がよくなっても自己判断で治療を中断しないようにすることが重要です。
国内では、一般的に抗菌薬の内服治療が行われてきました。神経梅毒などの場合は、抗菌薬の点滴により治療が行われます。
内服治療の場合、内服期間は医師が判断します。医師の許可を得るまでは、自己判断で内服を中断しないようにしましょう。
また、医師が安全と判断するまでは、性行為等の感染拡大につながる行為は控えましょう。
感染の可能性がある周囲の方(性行為のあるパートナー等)も検査を受け、必要に応じて治療を受けることが重要です。
梅毒の治療後
梅毒が完治しても、今後の新たな感染を予防できるわけではありません。梅毒は、何回でも感染する可能性のある感染症です。
適切な対策(コンドームの使用、パートナーの治療等)が取られていなければ、再び梅毒にかかる可能性があります。
梅毒の予防
自身の粘膜や皮膚が梅毒の病変と直接接触しないようにしましょう。病変の存在に気づかない場合もあることから、性交渉の際はコンドームを適切に使用しましょう。
ただし、コンドームで覆われない部分から感染する可能性もあるため、完全に予防できるわけではありません。
もし皮膚や粘膜に異常を認めた場合や気になる症状がある時には、性的な接触を控え、早めに医療機関を受診して相談しましょう。