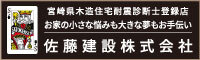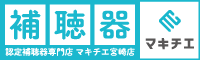令和7年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧のお知らせ
令和7年度分の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧が始まります。
◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
「宮崎市固定資産税納税者」は、土地・家屋価格等縦覧帳簿により本人の所有する土地又は家屋の評価額と市内全域の土地や家屋の評価額の比較ができます。
※縦覧を求めることができる人は納税者のみとなります。
期間
令和7年4月1日(火)~6月2日(月) (ただし、土、日曜日、祝日は除きます。)
※土地・家屋価格等縦覧簿の縦覧は窓口のみでの受付となります。
時間
午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時は除きます。)
ただし、6月2日は窓口対応時間短縮のため午前8時45分~午後4時30分
場所
市役所第3庁舎2階 資産税課、総合支所
◆固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者のほか、借地・借家人や処分の権利を有する一定の方も課税台帳の閲覧ができます。
期間
令和7年4月1日(火)~6月2日(月) (ただし、土、日曜日、祝日は除きます。)
時間
午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時は除きます。)
ただし、6月2日は窓口対応時間短縮のため午前8時45分~午後4時30分
場所
市役所第3庁舎2階 資産税課、総合支所、地域センター、地域事務所(中央東、東大宮、檍、大淀、大塚、大塚台のみ)
- この期間に限り、令和7年度分については無料で閲覧できます。
- この期間に限り、令和7年度分については市民課証明窓口、市民サービスコーナーでは閲覧できません。(この期間以外は有料での取り扱いとなります。)
- 各固定資産税関係証明(評価証明、公課証明、固定資産課税台帳記載事項証明等)の交付及び、令和7年度以外の課税台帳の閲覧は資産税課では取り扱いできません。通常どおり、市民課税証明窓口等で有料での取り扱いとなります。
| 閲覧を求めることができる人 | 閲覧できる固定資産 |
|
固定資産税の納税義務者 (納税義務者が亡くなられている場合は、その相続人) |
自己の所有する固定資産 (納税義務者が亡くなられている場合は、納税義務者の所有する固定資産) |
| 借地人 | 借地権のある土地 |
| 借家人 | 借りている家屋及びその敷地である土地 |
| 固定資産の処分をする権利を有する一定の人 | 権利のある固定資産 |
- 上記の閲覧を求めることができる人に加えて、民事訴訟等で訴えの提起等の申し立てをしようとする人も閲覧を求めることができます。(評価額のみ)
| 申請者 | 必要なもの |
| 固定資産税の納税義務者 |
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カードのような写真付き身分証明書など) ※納税義務者が亡くなられている場合は、相続確認ができる戸籍(写しでも可)の添付が必要です。 ※資産税課では戸籍の確認ができませんので必ず持参してください。 相続確認ができる戸籍とは…納税義務者の死亡日及び、相続人としての記載(配偶者・子など)があるもの。 |
|
借家人、借地人(閲覧のみ) |
・地主及び家主との借地、借家契約書の写し |
|
1月2日以降に新たに固定資産を取得した人(閲覧のみ) |
・固定資産売買契約書の写し及び領収書又は名義変更が行われた事の記載がある登記簿謄本等 |
|
固定資産の処分をする権利を有する一定の人(閲覧のみ) |
・その証する書類の写し |
- 代理人が申請される場合は、委任状又は納税義務者ごとの印鑑、代理人の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カードのような写真付き身分証明書など)が必要です。
- 法人の代表者が申請される場合は、法人印又は法人の代表者が確認できる商業登記簿等の写し及び代表者の本人確認書類が必要になります。法人の代表者以外の代理人が申請される場合は、委任状又は法人印、代理人の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カードのような写真付き身分証明書など)が必要です。
- 民事訴訟等で訴えの提起等の申し立てをしようとする人が閲覧を求める場合は、関係書類の写しが必要です。
郵送請求でのお手続きの方法
(1)申請書(課税台帳閲覧申請書(郵送用) (PDF 142KB)、記入例(郵送用) (PDF 77.5KB))
(2)添付資料
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、健康保険証など)の写しで返送先の住所の記載があるもの。
- 法人代表者の場合、法人印又は代表者の記載のある商業登記簿の写し※法人分のご請求の場合、申請代理人がその法人に所属することが分かる書類の写し(社員証、健康保険証等)及び本人確認書類(上記のもの)の写し※司法書士、弁護士の方が代理人として請求される場合、職印の押印又は資格証明書類写しの添付
- 返信用封筒(送付先の住所・宛名記入のうえ、切手を貼ったもの※不足分は申請者負担)※1月2日以降に固定資産を取得した方や、借地人、借家人、固定資産の処分の権利を有する方などは別途書類(固定資産売買契約書の写し及び領収書又は名義変更が行われた事の記載がある登記簿謄本等)が必要になります。
- 納税義務者が亡くなられている場合は、相続確認ができる戸籍(写しでも可)の添付が必要です。※相続確認ができる戸籍とは…納税義務者の死亡日及び、相続人としての記載(配偶者・子など)があるもの。
- 申請書及び上記資料を同封の上、資産税課にお送りください。
※借地人、借家人の方が借用している固定資産についての請求をされる場合には、公課証明(認証文なし)による回答となります。
※正式な公課証明(認証文あり)が必要な場合は、市民課証明係へご請求ください。
(窓口請求用)
課税台帳閲覧兼縦覧帳簿縦覧申請書(資産税課・総合支所用) (PDF 133KB)
課税台帳閲覧兼縦覧帳簿縦覧申請書(地域センター・事務所用) (PDF 133KB)
(郵送請求用)
(委任状)
令和7年6月3日(火)からは、通常どおり下記窓口で有料にて閲覧できます。
市役所市民課証明窓口、総合支所、地域センター、地域事務所(中央東、東大宮、檍、大淀、大塚、大塚台のみ)、市民サービスコーナー
※閲覧手数料として、一名義につき300円が必要となります。
※6月3日(火)から資産税課では閲覧ができなくなります。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
※未登記の建物についても登記の義務がありますので、相続登記の義務化が適用されます。